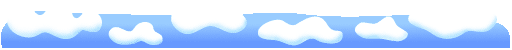
国境での話 その1
西ドイツのホーフという国境の町から東ドイツのドレスデン行きの電車に乗ったのは、忘れもしない
1974年7月21日のことだった。
1973年に東西ドイツが国連に加盟、日本‐東独間で国交正常化が行なわれたのを記念して
ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(ドレスデン・シュターツカペレ)が日本を演奏旅行した際、演奏会後に
楽屋まで押しかけて行き、M氏と無理やり知り合いになってもらったのだが、その際に、もしかしたら
来年の74年に運が良ければ、ドイツに行けるかも知れない、と話していたのだった。
奇跡的にそれが実現し、赤坂のドイツ民主共和国(東ドイツ)大使館を最初に訪れた際には、
「簡単ですよ。フランクフルトから東独行きの列車に乗るだけです」,と説明されたのだが、二度目には,
「それじゃだめです。それじゃだめです」、と応対され、「受け入れ先の招待状が要る」ということと、
「ホーフからグーテンフュルストの検問所を超えるように」、と言われ、M氏から頂いた、「藤島氏をゲストとして
お迎えします」、という招待状を頂き、ホーフのユースホステルに前泊して、ヴィザのないまま、
入国できるかどうかも全く分からない状態でドレスデン行きの列車に乗り込んだのである。
10分ほど走ったろうか。どこが国境か分からないままに列車はゆっくり走り始めた。
島国に育った日本人にとっては陸上の国境を超える、ということは全く想像もできない事である。
ましてや共産圏に入るのである。
しかしながら、どう言うわけか、あまり緊張はしていなかったように記憶している。
やがて列車が停止し、警察犬を連れた国境警察が入って来た。
一人ずつパスポート検査をしている。とうとう私の番がやって来た。
私は知っている限りのドイツ語を駆使して自分の立場を説明したのだった。
「私はヴィザを持っていなく、ここまではヴィザなしでオーケーですね?それでドレスデンの友達から招待状をもらって
いるんです。これで入国できませんか?大使館からはそうしなさい、と言われたのです」、というような事を説明した(と思う)。
国境警察官は一生懸命私のひどいドイツ語での説明を理解しようとしてくれたようで、「荷物を持ってここで下りなさい」、
と指示したのだった。
7月のすがすがしい快晴の日であった。
私は一人プラットホームに下り、5分ほど待たされた後に警察官の一人に着いて来る様に言われ、歩いて行く途中で
お茶を配っている赤十字の叔母さんに、「これはお茶ですか?」、と声をかけた所、「欲しいですか?」、と紙コップに入れた
お茶を差し出してくれた。
聞けば無料だと言う。
「信じられない。日本では何でも金がかかりますから。ダンケ!」
そして警察官にこの施設の小さな部屋に案内され、ここでしばらく待っている様に、と指示されたのだった。
本当に自分でも驚くぐらいに落ち着いていた。
後で考えたのだが、、日本人が入国するにはヴィザが要る、という規定があるにせよ、実際にはどう扱っていいのか
国境警察もはっきりとは分からなかったのだろう。
「とにかくこの日本人が持っている招待状の差出人に確認してみよう、」、という事で、国境警察はドレスデンの警察に
電話をし、実際にM氏に確認してくれる様に依頼したのだった。
M氏はこの日、自宅の庭で花壇の手入れをしていたのだが、そこへパトカーがやって来て、警官が「貴方は小さな日本人を
招待しませんでしたか?」、と問いかけたのである。
「ええ、間違いありません。でも彼は一体どこにいるんですか?」
「我々にも分かりません」
こうしてドレスデンの警察は国境警察に間違いない旨、報告したのだった。
困ったのはM氏である。
この小さな日本人がどこにいるのか分からないのである。
「どこかの国境にいるだろうから、西ドイツからドレスデンに来る列車を迎えに行ってみよう」、と考えたのだった。
さて、国境で足止めを食った私は1時間半ほど待たされただろうか。
乗って来た列車はとっくに去っていた。
机に頭を乗せてぼんやりしている所へ、警官がにこにこしながら入って来た。
「おお、疲れたのか?来なさい」
「ドレスデンへ行けますか?」
「ああ、もちろん!」
「ブラボー!!」
ちょうど次のドレスデン行きの列車が入って来ており、それに乗せられ、パスポートに入国ヴィザのスタンプを
押してもらった後、丁寧に荷物検査が行なわれた。
そして20マルクを東独マルクに両替してもらう。
こうした手続きを全て完了し、列車はドレスデンに向って動き始めた。
女性車掌が検札に来たのだが、切符を買うのを忘れていた。
聞けば21マルクだと言う。
20マルクしか持ってない、と話したらまけてくれた。
非常に幸先のいい事である。
「日本人で東ドイツに入る。それも個人旅行という形で。こんな日本人は誰もいないだろう」。
何となく嬉しくなって来る(今から考えると、馬鹿の一念、というものだろう)。
ドレスデンの中央駅に到着し、下りたとたんに目に入ったのが、自動小銃を持った2人組の警官だった。
「なんでこんな所で自動小銃が要るんだ?」、と考えながら、M氏を捜し、それらしい人に声をかけるのだが見つからない。
まもなく後ろで「パパ」という声が聞こえ、それに続いて、[FUJISHIMA!]、という声がした。振り返るとM氏だった。
ちゃんと待っていてくれたのである。
「やっと着きました!!」
もう、うれしくて声にならない。
一緒にいたのは16才になる息子さんのトーマス君だった。
こうして私の最初の東ドイツ訪問はなんとか成功し、M氏宅には5日間お世話になったのである。
その6年後、M氏は私の音楽の師匠になった。

